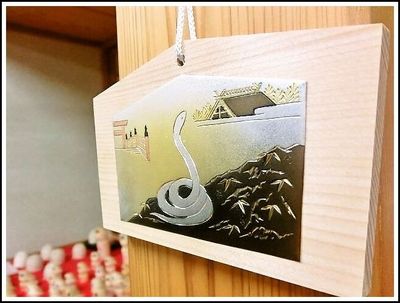2013年08月02日
☆龍笛・最近の状況☆
四十の手習いで始めた龍笛も、もうすぐまる二年になろうとしています
あれほど出なかった【責】(高音)もいつの間にか出るようになりました
なんかネットでいろいろ探して、参考になったのが唇の力を抜く…という
それを意識するようになったら、なんとなく歌口(吹き口)と吹く息の当たり具合が分かる様になりました
また、丹田に力を入れるという感覚もようやく分かってきました
現在、練習している曲は五常楽、平調、盤渉調の越殿楽、鷄徳、陪臚、合勧塩です
そうそう陪臚(ばいろ)はサンスクリット語(古代インド語)でヴィローチャナと言い、あの奈良の大仏毘盧遮那仏(大日如来)のことなんだそうです
神と仏が融合していた時代
まだまだ、曲の意味など分からずに吹いていますが、云われなんかも少しずつ調べていけば、もっと演奏してて楽しくなりそうな気がします

覚え書き
陰陽五行
木 東 春 朝 双調
火 南 夏 昼 黄鐘調
金 西 秋 夕 平調
水 北 冬 夜 盤渉調
土 中 土用 壱越調
(太食調は例外)
平調のみ越天楽と記し、他は越殿楽と記するのが慣わし
長慶子は源博雅の作
雅楽はもともと宴会を彩る楽舞だった
あれほど出なかった【責】(高音)もいつの間にか出るようになりました
なんかネットでいろいろ探して、参考になったのが唇の力を抜く…という
それを意識するようになったら、なんとなく歌口(吹き口)と吹く息の当たり具合が分かる様になりました
また、丹田に力を入れるという感覚もようやく分かってきました
現在、練習している曲は五常楽、平調、盤渉調の越殿楽、鷄徳、陪臚、合勧塩です
そうそう陪臚(ばいろ)はサンスクリット語(古代インド語)でヴィローチャナと言い、あの奈良の大仏毘盧遮那仏(大日如来)のことなんだそうです
神と仏が融合していた時代
まだまだ、曲の意味など分からずに吹いていますが、云われなんかも少しずつ調べていけば、もっと演奏してて楽しくなりそうな気がします

覚え書き
陰陽五行
木 東 春 朝 双調
火 南 夏 昼 黄鐘調
金 西 秋 夕 平調
水 北 冬 夜 盤渉調
土 中 土用 壱越調
(太食調は例外)
平調のみ越天楽と記し、他は越殿楽と記するのが慣わし
長慶子は源博雅の作
雅楽はもともと宴会を彩る楽舞だった
Posted by ☆ガGラ〃 at 11:57│Comments(0)
│手習い竜田揚げ